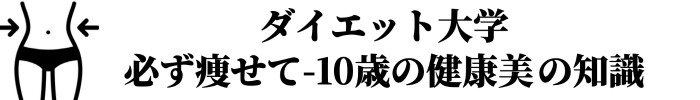チョコレートって食欲をおさえてくれるの?
なんでチョコレートが食欲をおさえるの?
こんにちは、おっちーです(^^)
あの口の中でとろける甘くて美味しいチョコレート🍫♪(๑´ڡ`๑)
チョコって太るイメージがあり、ダイエット中は食べてはならないものだと思いますよね。
でも、もしかしたらチョコレートは食欲をおさえてくれるかもしれません!
食欲はダイエッターにとって悩みのタネ。
あの美味しいチョコレートが食欲をおさえてくれるのなら、こんなに「お・い・し・い♪話」はありません!
そこで、今回のテーマはチョコレートは食欲をおさえるのか?問題について取り組みたいと思います。
この「チョコレートは食欲をおさえるのか?問題」をハッキリさせるために、論文を6本熟読しました。
よって、情報の質には自信があります!
この記事では、
- チョコレートが食欲をおさえるメカニズム
- チョコレートが本当に食欲をおさえるのか?実際の研究事例
について詳しく解説しています。
これを読めば、あなたはチョコレートは食欲をおさえるのか?本当のところがわかるでしょう。
それではいってみましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
チョコレートが食欲をおさえるって本当?

チョコレートは本当に食欲をおさえてくれるのでしょうか?
結論から入ります。
チョコレートは食欲をおさえます!だけどカロリーが・・・。
です。
なぜ、チョコレートが食欲をおさえるのか?
それは、
- カカオに含まれるココアバターが食欲をおさえてくれる
- カカオに含まれるポリフェノール(エピカテキン)が食欲をおさえてくれる
からです。
しかし、やっぱりカロリーが高いのが難しいところ。
詳しく解説します。
チョコレートのカカオが食欲をおさえる
カカオは、中央アメリカから南アメリカの熱帯地域を原産とするカカオの木から採集されます。
ココアやチョコレートの原料となるカカオマスは、カカオの実から胚乳部分を粉砕・焙煎してすり潰したもの。
このカカオマスから、ココアパウダー、ココアバターが作られ、これらに砂糖やミルクを加えることで最終的にチョコレートになります。
チョコレートの約50%は脂質ですが、それ以外の成分として食物繊維やポリフェノールが含まれています。
ポリフェノールには、フラボノイドの1種であるエピカテキンやプロシアニジンなどのカテキンが含まれています。
その他、テオブロミンやカフェインも成分として含まれています。
チョコレートの中でもダークチョコレート、いわゆる70%ハイカカオチョコレートはカカオが豊富に含まれています。
で、食欲に関係してくるのはココアバターと、ポリフェノールのエピカテキンです。
カカオの食欲をおさえるメカニズム

では、具体的にカカオがどうやって食欲をおさえるのか見ていきましょう。
ポイントは、
- カカオに含まれるココアバターが食欲をおさえてくれる
- カカオに含まれるポリフェノール(エピカテキン)が食欲をおさえてくれる
の2つです。
カカオに含まれるココアバターが食欲をおさえる
カカオに含まれるココアバターは食欲をおさえてくれます。
そのメカニズムは下記のとおり。
- ココアバターの脂質であるステアリン酸(飽和脂肪酸)は、腸での吸収が遅い
- 吸収が遅いから、腸にステアリン酸(飽和脂肪酸)が多く残る
- 腸にステアリン酸(飽和脂肪酸)が多く残ると、食欲をおさえるホルモンの「コレシストキニン」と「GLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)」の分泌が増える
- また、満腹感を与える「ペプチドYY」も増える
参考:ダークチョコレートとミルクチョコレートの食べ比べ:食欲とエネルギー摂取に及ぼす影響に関する無作為クロスオーバー試験(2011年12月)
脂肪量はミルクチョコレートよりもダークチョコレートで24%多く、ミルクチョコレートがココアバターとバター脂肪を含むのに対し、ダークチョコレート中の脂肪はココアバターだけだった。
ココアバター(チョコレート)は血中脂質に対して中立的な効果を持つことが研究で示されており11、これはステアリン酸を多く含むため(32-36%)、通過時間を遅らせるか消化率を下げるためであると考えられている11。
もし、ココアバターを多く含むダークチョコレートの消化管(腸)の通過時間が長ければ、消化管(腸)での脂肪の吸収が遅れることになる。
脂肪の吸収が遅れると、消化管(腸)に未消化の脂肪酸が多く残り、コレシストキニン、グルカゴン様ペプチド-1、ペプチドYYなどの食欲調節消化管ホルモンの放出が増加すると考えられる13、14、15。
ココアバターは脂質(飽和脂肪酸)ですが、ちょっと特殊で胃腸の通過時間が長く、なかなか吸収されず腸に残るといった性質を持っています。
これにより、「コレシストキニン、GLP-1、ペプチドYY」が分泌されます。
コレシストキニン、GLP-1、ペプチドYYは食欲を満たすホルモン。
これらのホルモンが食欲を満たすといった流れです。
このことから、カカオに含まれるココアバターは食欲をおさえるホルモンを分泌し食欲をおさえるといえることができます。
カカオに含まれるポリフェノール(エピカテキン)が食欲をおさえる
そして、カカオに含まれるポリフェノール(エピカテキン)も食欲をおさえてくれます。
エピカテキンとは、フラボノイド系のフラバノール類に分類されるカテキンの一種です。
緑茶に含まれるポリフェノールですが、カカオにもエピカテキンが含まれています。
カテキンは、「抗酸化作用、抗菌・抗ウイルス作用、抗がん作用、コレステロールを下げる、血糖の上昇をおさえる」といった嬉しい効果を持っています。
さらに、食欲までおさえてくれるナイスな成分。
下記のランダム化比較試験では、エピカテキン入りのココアはピザの摂取量を18.7%減らしたと報告しています。
※ココアの原料はカカオなので「ココア=チョコレート」です。
参考:エピカテキン、プロシアニジン、ココアと食欲:ランダム化比較試験(2016年9月)
【目的】
我々は、プラシーボ(エピカテキンまたはプロシアニジンを本質的に含まないアルカリ化ココア混合物)と比較して、以下の飲料が食欲の減少を引き起こすという仮説を検証することを目指した。
1)非アルカリ化ココア混合物の飲料、
2)エピカテキンとプラシーボの混合物の飲料、
3)プロシアニジンとプラシーボの混合物の飲料。
すべての飲料に含まれるカカオ化合物の濃度を測定した。
※飲み物の容量は体重に比例して計算されています。
【デザイン】
28人の健康な若年成人男性を対象に、期間および持ち越し効果のバランスを考慮した4ウェイ無作為クロスオーバー、プラシーボ対照試験を実施した。
食欲の主要な測定は、飲料摂取の150分後の自由食のピザ摂取量とした。
【結果】
エピカテキン(1.6mg/kg体重)を含む無アルカリ化ココア混合物の組み合わせは、ピザ摂取量を有意に18.7%減少させた(P = 0.04)。
【結論】
エピカテキンを添加した非アルカリ化ココア混合物は、食事摂取量の急性減少に関与していることが示された。
1.6mg/kg体重以上のエピカテキンは、単独または適切な触媒カカオ化合物と併用することで、食事摂取量のコントロールを助けるのに有用である可能性がある。
試験は、誰が何を飲んだか分からない状態(盲検化)にして、プラシーボ(思い込みによる効果)が起こらないようにデザインされています。
また、与えられた飲料のカロリーや栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂質、ミネラル)は、体重に基づき全て均一に調整しているという徹底ぶり。
その結果、体重×1.6mgのエピカテキンが、ピザの食べる量を18.7%減らしたという結果になりました。
※体重が55kgの場合、「55kg×1.6mg=88mg」
詳細なメカニズムの解明が待たれますが、ランダム化比較試験という厳格な試験においてエピカテキンは食べる量を減らしたようです。
このことから、カカオに含まれるエピカテキンは食欲をおさえるといってよいでしょう。
チョコレートが本当に食欲をおさえるのか?実際の研究事例

チョコレートが食欲をおさえるメカニズムについてわかりました。
それでは、実際にチョコレートは食欲をおさえることができるのか?実際の研究事例を見ていきましょう。
下記の研究は、朝にチョコレートを100g食べると300kcal/日、夜にチョコレートを食べると150kcal/日の食事量が減ると報告しています。
参考:チョコレート摂取のタイミングは、空腹感、基質酸化、微生物叢に影響を与える。無作為化比較試験(2021年7月)
チョコレートを朝または夕方・夜に食べると、エネルギー摂取量、基質酸化(エネルギーを生み出す)、腸内細菌(組成・機能)、概日関連変数の変化により、エネルギーバランスに差が出て、体重に影響を与える可能性がある。
ランダム化比較試験において、閉経後女性19名は2週間、朝(MC)、夕方/夜(EC)に100gのチョコレートを食べ、その他の食品は自由摂取とした。
その結果、14日間のチョコレート摂取は体重を増加させないことがわかった。
チョコレート摂取は空腹感および甘いものへの欲求を減少させ(P < 0.005)、自由摂取エネルギー量は朝(MC)では〜300 kcal/日、夕方/夜(EC)では〜150 kcal/日減少させた(P = 0.01)。
しかし、チョコレートがもたらす余分のエネルギー寄与(542 kcal/日)を十分に補うには至らなかった。
夕方/夜(EC)は、身体活動を+6.9%、食後の熱放散を+1.3%、炭水化物酸化を+35.3%増加させた(P < .05)。
朝(MC)は空腹時血糖値(4.4%)とウエスト周囲径(-1.7%)を減少させ、脂質の酸化を増加させた(+25.6%)。
主成分分析により、チョコレート摂取の両タイミングで、微生物叢のプロファイルと機能に差があることが示された(P < 0.05)。
手首の温度と睡眠記録のヒートマップから、夕方/夜(EC)は朝(MC)よりも規則的な睡眠を誘発し、日による入眠のばらつきが小さいことがわかった(60分 vs 78分;P = 0.028)。
結論として、朝または夕方・夜にチョコレートを食べると、空腹感・食欲、基質酸化(エネルギーを生み出す)、空腹時グルコース、腸内細菌(組成と機能)、睡眠・体温リズムに異なる影響が生じることがわかった。
この実験で使用されたのは、ダークチョコレートではなく、ミルクチョコレートです。
朝にチョコレートを食べると、1日300kcalの食事量が減る。
しかし、
”チョコレート100gのカロリー(542kcal)を補うまでにはいたっていません”
という、「言われてみればそりゃそうだろう」という衝撃の事実。
せっかく食事量が減ったにも関わらず、チョコレートそのもののカロリーで食欲をおさえる効果がお亡くなりになりました・・・。って、意味ないじゃん。
う〜ん、、、残念。。。
それでも、毎日チョコレートを100g食べてるにも関わらず14日間太ることはなかったというのが朗報でしょう。
さらに、朝にチョコレートを食べるとウエストが-1.7%減少し、脂肪燃焼を25.6%(脂質の酸化)増やしたというのも希望が持てるお話しです。
ちなみにダークチョコレートは、ミルクチョコレートより食欲をおさえることがわかっています。
参考:ダークチョコレートとミルクチョコレートの食べ比べ:食欲とエネルギー摂取に及ぼす影響に関する無作為クロスオーバー試験(2011年12月)
参考:β-グルカンとダークチョコレート:短期的な満腹感とエネルギー摂取に関する無作為クロスオーバー試験(2014年9月)
ダークチョコレートなら、もう少し良い結果がでたのでは?
※残念ながらダークチョコレートを使った食欲を計測する研究は見当たりませんでした。
以上のことから、チョコレートは食欲をおさえることはできるけどカロリーが高いので微妙といった感じになっちゃいました。
途中までチョコいけるんじゃね?と思ってたのですが、最後の最後でひっくり返されました^^;
以上、チョコレートは食欲をおさえるのか?問題に取り組みました。
結論は、
チョコレートは食欲をおさえます!だけどカロリーが・・・。
です。
残念ながら、チョコ食べてガンガン痩せようぜ!とまではいえません。
どうしても食欲がおさまらず、食べすぎてしまう!
といった場合、ケーキ、ドーナツ、ポテチ、スナック菓子に走るぐらいならチョコレートに走った方がよいといった感じですね♪
まとめ
最後にもう一度内容を確認しましょう。
- チョコレートの原料はカカオの実から作られるカカオマス
- カカオマスからココアパウダー、ココアバターが作られ、これらに砂糖やミルクを加えることでチョコレートになる
- チョコレートの約50%は脂質だが、それ以外の成分として食物繊維やポリフェノールが含まれる
- ポリフェノールには、フラボノイドの1種であるエピカテキンやプロシアニジンなどのカテキンが含まれている
- カカオに含まれるココアバターのステアリン酸が食欲をおさえるホルモンの分泌をうながし食欲をおさえる
- カカオに含まれるエピカテキンが食欲をおさえる
- 実際の研究ではチョコレートは食欲をおさえたが、チョコレートの高いカロリーにより食欲をおさえる効果が無駄になった(でも太ることはなかった)
いかがでしたでしょうか?
チョコレートは食欲をおさえてくれます。
しかし、チョコレートそのものの高カロリーは、いくら食欲をおさえてくれたとしてもダイエット効果としては微妙。
ただ、ケーキやドーナツ、その他の高カロリーの食べ物はチョコレートのような食欲をおさえてくれる効果はありません。
もし、食欲がとまらない!
といった場合はチョコレートを頼っていいと思います。
今回の記事で、チョコレートは食欲をおさえるのか?本当のところをご理解いただけたかと思います。
今回のお話は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
それではまた♪