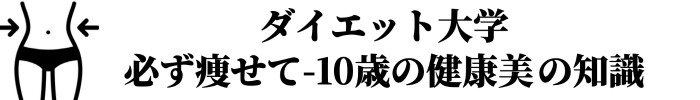こんにちは、おっちーです^^
今回も必ずやせて-10歳の健康美を手に入れるための「ダイエットの基礎知識」を学んでいきます。
前回は「身体活動レベルから導く1日の総消費カロリー(TDEE)」について学びました。
こんにちは、おっちーです^^今回も必ずやせて-10歳の健康美を手に入れるための「ダイエットの基礎知識」を学んでいきます。 前回は「基礎代謝とは?」というテーマで、やせるカラダの土台作りについて学びました。[…]
これにより、1日の総消費カロリー(TDEE)がわかり、1日にどれくらい食べればやせられるのかの現実的なところが掴めたかと思います。
今回は、「肥満遺伝子」について学びます。
本記事を読むことで、肥満遺伝子について理解が深まると思います。
最近は肥満遺伝子を簡単に検査できるようになっているみたいですね。
もし、自分の肥満遺伝子がわかるのであれば、ダイエットの戦略が立てやすくなるかもしれません。
では、結論です。
確かに
・遺伝によって太りやすい人はいる。
そして、
・日本人は太りやすい遺伝子を受け継いでいる。
です。
それでは詳しく見ていきましょう!
肥満遺伝子とは
肥満遺伝子とは、肥満に関連する遺伝子のことです。
食事を減らしても体重が減りにくい人、たくさん食べても太りにくい人がいます。
肥満の原因として、遺伝子の影響は30%〜40%と考えられています。
※それなりに影響がありますね・・・。
具体的な事例として、
- 双子の参加者を対象に遺伝と減量の関係を調査:7組の一卵双生児の双子(若年成人男性)に93日間、同じ食事とエクササイズをしてもらったところ、ある双子は2kgの減量で、別の双子は8kgの減量と4倍の差がでた。内蔵脂肪はある双子は-10c㎡の減少で別の双子は-50c㎡の減少と5倍の差がでた。
- 双子の参加者を対象に遺伝と過食に対する反応を調査:12組の一卵双生児の双子(若年成人男性)に100日間、同じ食事(過食)をしてもらったところ、ある双子は4.3kgの増量で、別の双子は13.3kgと約3倍の差がでた。内臓脂肪はある双子は+10c㎡の増加で別の双子は+45c㎡の増加と4.5倍の差がでた。
- 遺伝による脂肪のつきやすい部位の調査:体の全体(胸、腹、背中、腕、もも)に脂肪がつきやすいタイプと、ウエストにつきやすいタイプ、腹回りと下半身に脂肪がつきやすいタイプに分けられた。
などがあります。
これらの事例から、遺伝による「太りやすい太りにくい」、「やせやすいやせにくい」があることがわかります。
主な肥満遺伝子と日本人の割合
肥満に関連する遺伝子は50種類以上あると言われていますが、ここでは代表的なものを4つあげます。
β3アドレナリン受容体(ADRB3)
「β3アドレナリン受容体」が「変異型」の遺伝子を持つ人は、基礎代謝量が低くなり太りやすくなると言われています。
激しい感情や肉体作業などでカラダがストレスを感じると、交感神経の情報伝達物質としてノルアドレナリンが放出されます。
このノルアドレナリンは各臓器の細胞表面にある「アドレナリン受容体」を刺激し、脂肪の分解と熱産生を促します。
β3アドレナリン受容体は、主に脂肪細胞に存在し「野生型」と「変異型」の2つのタイプに分けられます。
同レベルのノルアドレナリンの刺激であっても「野生型」は脂肪を多く分解しますが、「変異型」はあまり脂肪を分解しません。
日本人の約30%〜40%は「変異型」のβ3アドレナリン受容体を持っています。
「変異型」は進化の過程で飢餓に対応するためには非常に優秀な遺伝子ですが、飽食の時代である現代においては逆に肥満を招く結果となってしまっています。
UCP-1(脱共役タンパク)
「UCP-1(脱共役タンパク)」を作れない遺伝子の人は、基礎代謝量が低くなり太りやすくなると言われています。
人のカラダは、36.5度前後をキープするように調節されています。
この体温を維持するために、褐色脂肪細胞のミトコンドリアで脂肪を燃焼させています。
この脂肪を燃焼させるのに必要なタンパク質が「UCP-1(脱共役タンパク)」です。
※ノルアドレナリンが、上記の「β3アドレナリン受容体」に結合されると「UCP-1」が作られます。
で、日本人はこの「UCP-1(脱共役タンパク)」を作れない人が約20%いるそうです。
これが作られなければ、「UCP-1(脱共役タンパク)」による脂肪燃焼は得られないので「太りやすく」なります。
また、「低体温・冷え性」の人は「UCP-1(脱共役タンパク)」による熱が作られないため、このタイプに当てはまるのかもしれません。
参考:ミトコンドリア脱共役蛋白質UCPファミリーとエネルギー消費・肥満(1999年)
β2アドレナリン受容体(ADRB2)
「β2アドレナリン受容体」が「変異型」の遺伝子を持つ人は、基礎代謝量が高くなりやせやすくなると言われています。
「β3アドレナリン受容体」とは真逆の関係にあります。
「β2アドレナリン受容体」は、心臓や気管支に存在しており、血管や気管支の弛緩(ゆるめたり、たるめたり)に関係しています。
この血管や気管をゆるめることにもエネルギーが必要で、脂肪を分解してエネルギーを抽出することで代謝がアップします。
FTO遺伝子(rs9939609、rs1558902)
「FTO遺伝子(FTO:fat mass and obesity associated)」。
この遺伝子の「変異型」を持っている人は、食欲をおさえることが難しくなり、特に高カロリーの食品を好む傾向が強くなると言われています。
「グレリン」は胃から分泌されるホルモンで食欲を司っています。
FTO遺伝子の「変異型」の人は、この食欲ホルモンである「グレリン」の異常が起こりやすく、食事をした後でもすぐに食欲を感じやすい傾向があります。
また、高カロリーの食事やスナック類の摂取量が多く、脂質が高くなる傾向があると言われています。
6人に1人がFTO遺伝子の「変異型」を持っていると言われてますが、運動を増やせばこの肥満遺伝子の影響を取り除けることがわかっています。
肥満遺伝子を測定できる!?
自分の肥満遺伝子を把握し、どういう体質なのかを知る。
もし、自分の体質がわかるのであれば、
- 何に気をつけなければならないのか?
- どうすればいいのか?
ダイエット戦略をたてる上で非常に参考になるのではないでしょうか。
体質がわからないまま、対策をとっても実は効果が期待できないものであったり、意味がないものになるかもしれません。
肥満遺伝子を検査し自分の体質を把握すれば、このような結果のでない方法で時間と労力を無駄にすることはなくなると思います。
まとめ
以上、「肥満遺伝子」について学んできました。
確かに
・遺伝によって太りやすい人はいる。
そして、
・日本人は太りやすい遺伝子を受け継いでいる。
ということをご理解いただけたかと思います。
これだけ見てしまうと「あぁ〜、やせるのはやっぱりムリなのね・・・」と肩を落としてしまうかもしれません。
確かに肥満の原因は遺伝による先天的なものが30%〜40%を占めますが、残りの60〜70%は後天的な環境によるものです。
つまり、遺伝よりも普段の食生活と運動習慣の方が影響が大きいということになります。
今回のお話はここまでですが、次回のお話で残りの60〜70%である後天的な環境について具体的にお話ししたいと思います。
それではまた♪