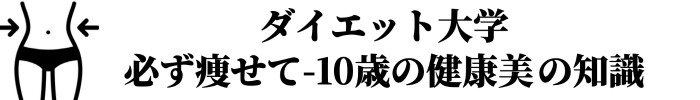体内時計ってなんで狂うの?
体内時計が狂う原因を知りたい!
こんにちは、おっちーです(^^)
前回の記事では、体内時計が狂うと「肥満、糖尿病、動脈硬化→心筋梗塞・脳卒中、がん、睡眠障害」になるとお伝えしました。
※まだお読みでなければ先にコチラをお読みください。
体内時計が狂うとどんな病気になるの?そもそも体内時計ってなに? こんにちは、おっちーです(^^) 体内時計って聞いたことあるでしょうか?「なんか聞いたことあるけど詳しくは・[…]
実は、この記事の体内時計が狂う原因を読み進めれば、これらの病気の対策がうてるようになります。
なぜなら、ここでご紹介するのは論文12本の中から体内時計が狂う原因をピックアップし具体的になっているからです。
この記事では、
- 体内時計を狂わす原因4つ
について解説しています。
これを読み終えれば、あなたは体内時計が狂う原因を知ることができるでしょう。
原因を知り対策を打つことで、これ以上体内時計が狂うことはありません。
体内時計が狂わないということは、「肥満、糖尿病、動脈硬化→心筋梗塞・脳梗塞、がん、睡眠障害」といった病気の予防につながります。
それではいってみましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
体内時計が狂う原因は4つ!

体内時計が狂う原因は、
- 夜に光を浴びる
- 寝る前のブルーライト
- 寝る3時間前のカフェイン
- 高脂肪食(近代型の欧米食)
の4つです。
体内時計が狂うのを防ぐためには、この4つの原因を生活習慣から取り除くことが重要です。
原因1:夜に光を浴びる
体内時計が狂う一番の原因は、夜に光を浴びることです。
地球上の生命は、太陽の光とともに生きています。
人であれば、日中に活動し夜に眠るというのが基本的な概日リズムです。
で、この仕組みを支えているのがメラトニン。
体内時計が狂うとどんな病気になるの?そもそも体内時計ってなに? こんにちは、おっちーです(^^) 体内時計って聞いたことあるでしょうか?「なんか聞いたことあるけど詳しくは・[…]
この記事の睡眠障害のところで触れましたが、メラトニンは睡眠を誘発する脳の松果体から分泌されるホルモンです。
メラトニンは、体内時計を調節する重要なホルモンです。
特に、体内時計のマスタークロックである中枢時計を調節する働きがあります。
メラトニンは、目の網膜から入った明暗の光刺激が、脳の視床下部の視交叉上核(中枢時計)を経由して松果体へ伝達することで、分泌が促されたり抑制されたりします。
- 日中:松果体が明るさを感じると、メラトニンの分泌は抑制される
- 夜間:松果体が暗さを感じると、メラトニンが分泌される
これがメラトニンの性質です。
しかし、現代は24時間365日の休み知らずの社会。
24時間営業のコンビニの店内の明るさは1,000〜2,000ルクスと、日中の晴天時の室内の窓際と変わらない明るさです。
これだけの明るさを浴びると、いくら夜間といえど脳は昼間と勘違いしてしまいメラトニンの分泌が抑制されてしまいます。
で、どのくらいの光の量を浴びるとメラトニンが抑制されるかというと、
参考:光によるヒトのメラトニン抑制は強度依存性である(1989年)
5種類の人工光の強度が夜間のメラトニン濃度に及ぼす影響について検討した。
深夜1時間の光照射によるメラトニンの最大抑制率は、それぞれ3,000(71%)、1,000(67%)、500(44%)、350(38%)、200(16%)ルクス(lx)であった。
強度1,000ルクス(lx)の光はメラトニンを日中レベル近くまで抑制するのに十分であり、強度350 lxまでは夜間のメラトニンレベルを点灯前の値以下に有意に抑制することが示された。
夜に1,000ルクス(コンビニの店内の明るさ)を1時間浴びると、メラトニンの分泌は抑制されてしまうとのことでした。
また、メラトニンが抑制されるのは光にあたる時間も重要で、500ルクス(一般の住宅の勉強部屋)を2時間浴びると、1時間1000ルクス浴びるのと同じことになります。
そして、下記の研究では室内光程度の明るさでも浴び続けていると、メラトニンが抑制されてしまうことを報告しています。
参考:就寝前に室内光を浴びるとメラトニンの発現が抑制され、メラトニンの持続時間が短くなることがヒトで判明(2011年3月)
【目的】
我々は、深夜に室内光を浴びるとメラトニン合成の開始が抑制され、メラトニン生成の持続時間が短くなるという仮説の検証を行った。
【デザイン】
室内光(200ルクス未満)と薄暗がり(3ルクス未満)で生活する人の1日のメラトニン量を比較した。
【介入】
就寝前8時間に室内光(200ルクス未満)または薄明かり(3ルクス未満)に曝露した。
【結果】
就寝前の室内光照射は、薄暗がりと比較してメラトニンを抑制し、99.0%の人でメラトニン発現が遅くなり、メラトニン持続時間が約90分短くなった。
また、通常の睡眠時間帯に室内光を照射すると、ほとんどの試験(85%)でメラトニンが50%以上抑制された。
【結論】
これらの知見は、室内光がメラトニンレベルに大きな抑制効果を及ぼし、夜間継続時間の体内表現を短縮することを示す。
したがって、深夜に慢性的に電気照明にさらされると、メラトニンのシグナル伝達が阻害され、睡眠、体温調節、血圧、グルコースのホメオスタシスに影響を及ぼす可能性がある。
メラトニンは、睡眠を含め体内時計を調節する重要なホルモンです。
夜の光は、メラトニンの分泌を低下させ体内時計を狂わす原因となります。
※200ルクス未満の弱い光であっても。
よって、体内時計を狂わさないためにも夜にできるだけ光を浴びないようにしましょう。
原因2:寝る前のブルーライト
夜寝る前にスマホを開き、Twitterやネットを徘徊するという人も多いのではないでしょうか。
実はコレ、体内時計にとって非常によろしくない行為です。
夜間にスマホのブルーライトを目に入れると、体内時計が狂います。
前章の夜の光と似たようなお話ですが、ブルーライトはまた特別です。
※室内がいくら暗くてもブルーライトを浴びれば体内時計が狂います。
ブルーライトは、テレビやパソコン、スマホから出る青い光で、この青い光(380〜500nm、ナノメートル)の波長がメラトニンの分泌を抑制し、睡眠の質を下げる最大の要因となっています。
下記の研究では、「446〜477nm」の青い光がメラトニンを抑制することを報告しています。
ヒトにおけるメラトニン調節のための作用スペクトル:新規な概日リズム光受容体の証拠(2001年8月)
本研究の目的は、ヒトの松果体を調節するための光によるメラトニン抑制の作用スペクトルを確立することであった。
被験者(女性37名、男性35名、平均年齢24.5±0.3歳)は健康で、正常な色覚を有していた。
夜間のメラトニン抑制試験は、420から600 nmの波長で完了した。
これらのデータから、メラトニン分泌を抑制するための概日入力を与える最も強力な波長領域として446-477 nmが同定された。
※ブルーライトは380〜500nm
この結果は、ヒトでは、単一の光色素がメラトニン抑制に主に関与している可能性を示唆しており、そのピーク吸光度は、視覚のための杆体および錐体細胞の光色素とは異なるようである。
これによると、メラトニンの分泌を最も抑制するのが「446nm〜477nm」の波長領域だそうです。
ブルーライトは「380nm〜500nm」の波長領域なので、ブルーライトが最もメラトニンを抑制すると言えます。
また、こちらの研究では、同じ明るさでもブルーライトがメラトニンを抑制すると述べています。
大学生におけるコンピューターモニターの光がメラトニン濃度に及ぼす影響について(2011年)
【目的】
自己発光型電子デバイスは、メラトニン抑制のピーク感度に近い短波長の光放射を行う。
夜間の光照射によるメラトニン抑制は、疾病のリスク上昇と関連することが知られている。
発光するコンピューターモニターがメラトニン抑制に与える影響について調査した。
【デザイン】
21名の参加者が3つの試験条件を体験した。
①コンピュータモニターのみ
②発光ダイオード(LED)から角膜に短波長(青色、ピークλ≒470nm)光を40ルクス照射するゴーグルを通して見るコンピュータモニター
③オレンジ色のメガネ(光放射<525nm≒0)を通して見るコンピュータモニター
※オレンジ色のメガネは、ブルーライトをカットします。
【結果】
「②ブルーライトゴーグル」のメラトニン濃度は、「①コンピューターモニターのみ」と「③オレンジ色のメガネ」と比較して、有意に減少した。
統計的に有意ではなかったが、「①コンピューターモニターのみ」の平均メラトニン濃度は、「③オレンジ色のメガネ」と比較してわずかに減少していた。
「①コンピューターのみ、②ブルーライトゴーグル、③オレンジ色のメガネ」と比べた結果、同じ明るさでも「②ブルーライトゴーグル」がメラトニンを抑制することがわかります。
メラトニンは体内時計を調節するホルモンです。
これらのことから、寝る前のブルーライトが体内時計を狂わす原因となります。
よって、体内時計を狂わさないためにも寝る前のスマホは控えましょう。
原因3:寝る3時間前のカフェイン
寝る3時間前のカフェインも体内時計を狂わす原因となります。
カフェインといえばコーヒー。
コーヒー1杯(150ml)でカフェインが75mg含まれています。
※ちなみに緑茶1杯(150ml)は30mgのカフェインが含まれています。
下記の研究では、カフェインが体内時計を遅延させると報告しています。
参考:カフェインがヒトの概日時計に及ぼす影響(in vivo および in vitro(2015年9月)
カフェインの覚醒促進作用と睡眠阻害作用はよく知られているが、カフェインがヒトの概日リズムに影響を与えるかどうかは不明である。
我々は、夕方のカフェイン摂取がヒトの概日リズムであるメラトニンリズムを遅延させること、またカフェインの慢性投与が主にアデノシン受容体/環状アデノシン一リン酸(AMP)依存機構により分子振動の概日周期を延長させることを明らかにした。
二重盲検プラセボ対照、約49日間の被験者内研究において、習慣的就寝の3時間前にダブルエスプレッソと同量のカフェインを摂取すると、概日リズムのメラトニン位相が約40分遅れることを見出した。
この遅延の大きさは、習慣的な就寝時刻に始まる夕方の明るい光(~3000ルクス、~7W/m(2))に3時間暴露することによって誘発される位相遅延反応の大きさのほぼ半分であった。
これらの結果は、カフェインがヒトの概日リズムに影響を与えることを示しており、世界で最も広く消費されている精神活性物質がヒトの生理機能に影響を与える1つの方法であることを示しています。
こちらでは、カフェイン(2.9mg/kg)を寝る3時間前に摂取すると、体内時計を40分遅延させるようです。
カフェイン「2.9mg/kg」とは、体重50kgの人であれば145mgのカフェイン。
ダブルエスプレッソと同じくらいのカフェイン量です。
さらに、この論文を深く読み込むことでわかったことは、
- ダブルエスプレッソを寝る3時間前に飲むと、体内時計が40分後ろにずれる
- ブルーライトのみでは、体内時計が85分遅延する
- カフェインとブルーライトを組み合わせは、105分も体内時計が遅延する
ということです。
※カフェインとブルーライトの組み合わせは体内時計へのダメージがでかい!(@_@;)
このことから、寝る3時間前のカフェインは体内時計を狂わせることがわかりました。
よって、体内時計を狂わせないためにも寝る3時間前のカフェインはさけましょう。
原因4:高脂肪食(近代型の欧米食)
最後に体内時計を狂わせる原因として、高脂肪食があります。
高脂肪食といえば、近代型の欧米食でしょう。
こんにちは、おっちーです^^今回も必ずやせて-10歳の健康美を手に入れるための「ダイエットの基礎知識」を学んでいきます。 前回は「肥満の歴史」というテーマで、なぜ人は太りやすくなったのか?について学びました[…]
この近代型の欧米食、体内時計を狂わせる他に
- 腸内環境を狂わせる
腸内環境を整えると何がいいの?腸活って何をすればいいの? こんにちは、おっちーです。(^^) 腸内環境を整えることはとても大切です。でも、腸内環境が大切と言われても「?」と[…]
- 体重のセットポイントを狂わせる
セットポイントって何?体重と関係あるの?痩せられるの? こんにちは、おっちーです(^^) 自動で痩せられる仕組みが手に入ったら嬉しいと思いませんか?そう、その鍵を握るのがセットポイ[…]
- 食欲が暴走する
なぜ食欲ってコントロールできなくなるの?食欲のコントロールってどうすればいいの?食べすぎで太らないようにするためには? こんにちは、おっちーです。 なぜ食欲がとまならくなる[…]
と、悪いことだらけ。
実際、下記のシステマティックレビューでは、高脂肪食が体内時計を狂わせるとまとめています。
※システマティックレビューとは、明確に作られたクエスチョン(高脂肪食は体内時計を狂わすのか?)に対し、順序立って組み立てられた方法を用いて適切な研究を選択、評価したもの。情報の質としては高い。
参考:高脂肪食は概日時計に影響を与えるのか、それとも逆なのか?システマティックレビュー(2020年12月)
【要旨】
本論文では、マウスの概日リズムに及ぼす食事の影響、ひいては体内時計の破壊とその代謝異常の発生における役割について取り上げた研究をレビューする。
PubMed電子データベースを用いた系統的検索により、過去14年間の研究を選択した。
その中から、マウスに高脂肪食を与える、時計遺伝子の発現を評価する、体内時計の破壊と脂質代謝異常との関連を評価する、などの条件を満たす291件の研究が選ばれた。
これらの研究では、動物が高脂肪食を摂取して代謝異常を発症すると、体内時計が変化することが報告されています。
また、いくつかの時計遺伝子の変異や欠失が代謝の変化を誘発することも明らかにされた。

概日時計と高脂肪食の相互作用は、全身の代謝だけでなく、多くの臓器や組織の代謝にも影響を及ぼす。
高脂肪食は体内時計に影響を与え、そのような食事による体脂肪の増加の結果は、恒常性と健康を変化させる体内時計の破壊に関連する要因に変換される。
代謝異常や現代人の典型的な生活習慣の悪影響が体内時計の破壊を引き起こし、脂質代謝異常や動脈硬化など。、生理、代謝、健康に関連する結果をもたらすようだ。
このシステマティックレビューでは、「高脂肪食は体内時計を狂わすか?」という問いに答えるために過去14年の研究から291件を抽出しています。
で、そこから得られた結論は高脂肪食(近代型の欧米食)が体内時計を狂わすです。
※上記のシステマティックレビューでは、高脂肪食によって体内時計を破壊するルートと、肥満による代謝障害によって体内時計を破壊する2つのルートがあると述べています。
このことから、高脂肪食は体内時計を狂わす原因といってよろしいでしょう。
よって、体内時計を狂わせないためにも高脂肪食はできるだけ控えましょう。
以上、体内時計が狂う原因について解説しました。
体内時計が狂う原因は、
- 夜に光を浴びる
- 寝る前のブルーライト
- 寝る3時間前のカフェイン
- 高脂肪食(近代型の欧米食)
の4つです。
まとめ
最後にもう一度内容を確認しましょう。
- 体内時計が狂う「原因1:夜に光を浴びる」は、メラトニンの分泌を低下させ体内時計を狂わせる
- 体内時計が狂う「原因2:寝る前のブルーライト」は、メラトニンの分泌をもっとも抑制する「446nm〜477nm」の青い光の波長が体内時計を狂わせる
- 体内時計が狂う「原因3:寝る3時間前にカフェイン」は、体内時計を40分遅延させることで体内時計を狂わせる
- 体内時計が狂う「原因4:高脂肪食(近代型の欧米食)」は、「高脂肪食は体内時計を狂わせるか?」という問いのシステマティックレビューで、YESという結論だった
今回の記事で体内時計が狂う原因を知ることができたのではないでしょうか。
原因を知りそれを取り除けば、これ以上体内時計が狂うことはありません。
体内時計が狂わければ、「肥満、糖尿病、動脈硬化→心筋梗塞・脳梗塞、がん、睡眠障害」といった病気の予防につながります。
今回は体内時計が狂う原因について解説しました。
これで体内時計が狂うことは防げると思います。
次回は、体内時計をリセットする方法について解説します。
体内時計をリセットすることができれば、あなたの体内時計はより整うことでしょう。
今回のお話はここまでです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
それではまた♪